社労士の資格に初めて挑戦してみるつもりだけど、あまり良く分かってないので、試験の頻度、範囲、合格率などについて詳しく知りたい、など思っていませんか?
この先をお読みいただければ、そのような思いをされている方々へ、参考となる情報をお伝えできると思います。
私は「社労士」資格を取得している人事担当者です。
ここでは社労士資格の試験概要などを、過去実施分を参考にしながら分かり易く説明して、これを見ればいつ、どこで、どんな試験が行われるかを一通り理解できる内容にしています。
自分が資格を取得した未来をイメージしながら、前を向いて進んでいきましょう!
社労士について
試験概要の説明の前に、社労士とは何なのかから始めます。
社労士とは
社労士は社会保険労務士の略称です。社会保険労務士法という法律があり、これの第2条には以下のような記述があります。
(社会保険労務士の業務) 第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて・・・
という感じで相当に長いので、細かいことは抜きにして言います。
社労士は、社会保険労務士法の定めに基づく国家資格で、労働保険や社会保険の専門家として、それらの業務を独占的に行うことが出来る士業です。
急に「独占的」や「士業」という言葉が出てきましたので補足します。
- 独占的:例えば会社に新人が入った時に、雇用保険の資格取得届をハローワークに提出しますが、社労士はこの届を行うことが出来る。弁理士や宅建士などは出来ない。
- 士業:弁理士や宅建士、税理士、行政書士など、〇〇士と呼ばれる〇〇を業(継続的に仕事をしてお金をもらう)としている人たちの仕事。
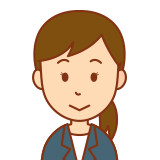
えっ、ちょっと待って
私は会社で雇用保険を担当して
ハローワークへ届出に行ったことあるけど
社労士じゃないのに
と思われたかもしれません。通常、会社がハローワークに届出する際には、会社の社長など代表者名(または代理人名)で提出します。会社で雇用保険を担当をしている方が、会社の社長名で提出するならば、何も社労士である必要はありません。
ただし、この会社が行う行為を、社労士が委託を受け「社会保険労務士の名前」で提出できるということです。
社労士の資格
後述する社会保険労務士試験に合格することで、社労士になる「資格」を得ることが出来ます。
注意しなければならないのは、あくまで「資格」を得るだけだということ。実際に「社会保険労務士」と名乗るためには「実務経験」と「登録」が必要です。

ぼくは社労士の資格を持ってるけど、
登録をしていないから社労士って
名乗れないんだって
詳細は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
社労士資格の試験実施主体
社会保険労務士法には試験の実施に関する定めもあり、第10条第2項には「ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。」とあります。
(試験の実施) 第十条 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
社労士試験は実質的に、全国社会保険労務士会連合会が実施主体です。覚えておきましょう。
社労士資格の試験概要
受験資格
社労士になるためには、国家資格を得るため試験に合格する必要があります。社会保険労務士法には受験資格が定められていて、第8条には以下のような記述があります。
(受験資格) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条・・・
これも長くて読むのが嫌になってしまうと思うので、根拠条文はここだと覚えてもらえれば十分かと思います。基本的には下表を抑えていただければ充分です。
| 区分 | 受検資格 |
| 大学・高専卒 | あり |
| 大学中退 | あり(ただし62単位以上修得が必要) |
| 短大卒 | あり(ただし全国社会保険労務士会連合会の審査が必要) |
| 専門学校卒 | あり(ただし修業年限2年以上で、総授業時間数1700時間以上が必要) |
| 高卒 | なし(実務経験が認められれば「あり」) |
| 司法試験1次合格者 | あり |
| 行政書士資格合格者 | あり |
上表で受験資格欄にただし書きがある「大学中退」「短大卒」「専門学校卒」「高卒」の場合は、念のため社会保険労務士試験オフィシャルサイトにお問い合わせいただくことが賢明だと思います。(TEL03-6225-4880)
受験資格についての詳細は、以下リンクから確認することが出来ます。
受験資格について | 社会保険労務士試験オフィシャルサイト (sharosi-siken.or.jp)
試験の範囲
社会保険労務士法には試験に関する定めもあり、第9条および第10条には以下のような記述があります。
(社会保険労務士試験) 第九条 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 労働基準法及び労働安全衛生法 二 労働者災害補償保険法 三 雇用保険法 三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 四 健康保険法 五 厚生年金保険法 六 国民年金法 七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 (試験の実施) 第十条 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
まずは試験の範囲について、上の根拠条文と全国社会保険労務士会連合会の案内を下表にまとめていますので、ご参照ください。
| 試験科目 | 選択式 計8科目(配点) | 択一式 計7科目(配点) |
| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する 法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する 法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 労務管理その他の労働に関する 一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | 上記と併せて |
| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
| 合計 | 8問(40点) | 70問(70点) |
合格基準点
選択式および択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定められます。各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となります(合格基準点は、合格発表日に公表されます。)。
上記を噛み砕きますと、以下のようになります。
- 合格ラインは毎年異なる
- 合格基準点として択一式では4割取らないと足切り
- 選択式は原則6割、ただし救済措置の可能性あり
合格率
過去10年の推移をご覧ください。6%程度(16人のうち1人合格)というイメージで良いかと思います。
| 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 合格率 | 7.0% | 5.4% | 9.3% | 2.6% | 4.4% | 6.8% | 6.3% | 6.6% | 6.4% | 7.9% |
試験の実施日
以下の根拠条文に記載のとおり年1回実施されます。試験の実施月は毎年一緒ですので、申し込み日と一緒にまとめておきます。
(試験の実施) 第十条 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
| 項目 | 実施月 | 備考 |
| 試験申込日 | 4~5月下旬 | インターネットまたは郵送にて |
| 試験実施日 | 8月下旬 |
試験の実施時間
試験時間に関しては、過去の実施分を参考に記載します。
| 項目 | 時間 | 備考 |
| 着席時刻(受験者集合) | 10:00 | |
| 注意事項説明、開始準備 | 10:00~10:30 | |
| 選択式試験 | 10:30~11:50 | 11:10~11:40は許可を得て退出可 |
| 昼食時間 | 11:50~12:50 | |
| 注意事項説明、開始準備 | 12:50~13:20 | |
| 択一式試験 | 13:20~16:50 | 14:10~16:40は許可を得て退出可 |
実施場所
最後に、共通ではない事項である試験の場所を説明します。
試験の実施は全国各地で行われます。例年を参考にすると以下のような感じです。
| 項目 | 場所 | 備考 |
| 試験地 | 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、 広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県 | 「希望試験地」は上記の都道府県から選択。 原則として希望した試験地だが、会場確保の 状況により、近隣の都道府県の会場となる場合あり |
| 試験会場 | 受験申込時にご希望いただいた試験地に基づき決定し、 後日に受験票でお知らせ | 試験会場に関する照会には応じられない |
各都道府県の会場の都合により毎年同じ場所という訳ではありません。
首都圏にお住まいの方であれば、例年試験会場は数多くあるので問題ないと思いますが、ここに記載の都道府県以外の場所へお住いの場合は、試験当日にお近くの試験地へ前泊する必要があるかもしれません。
その場合は、あらかじめ宿泊場所の確保などが必要となってきますので、事前の手配があることを念頭に入れておきましょう。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
いつ、どこで、どんな試験が行われるのか、今の段階ではおおよその概要を掴めていればOKだと思います。
- 社労士は国家資格で、社会保険労務士試験に合格することで社労士になれる「資格」を得るが、「登録」しないと社労士とは名乗れない
- 受験資格は、大学卒・高専卒は問題ないが、短大卒などは確認が必要で、高卒は実務経験があることを必要とする
- 試験の範囲と配点は毎年変わらないが、合格基準点は毎年異なり、足切りや救済措置される場合がある
- 試験実施日は8月下旬、申込は5月下旬まで
- 合格率は6%程度
- 試験時間は、選択式が午前で80分、択一式が午後で210分
- 試験の場所は全国各地で実施されるが、申込時点ではどの会場になるか分からない
内容の詳細については、4月に厚生労働省から公式発表される情報を確実に抑えてください。まずはそこからです。
それでは、順調なスタートが切れるよう、お祈りいたします!




コメント